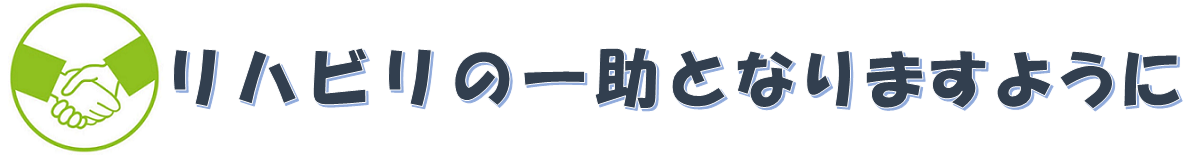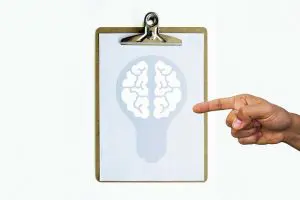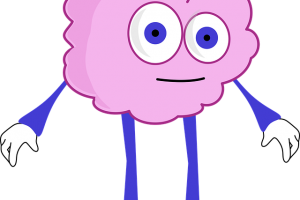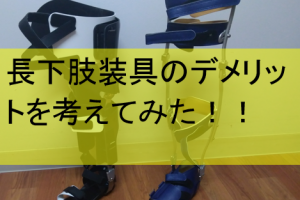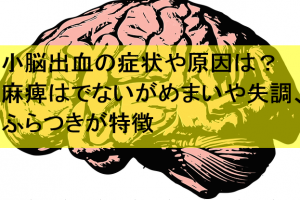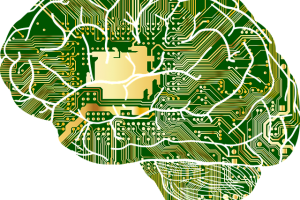Warning: Undefined array key 3 in /home/heyreha/heyreha.com/public_html/wp-content/themes/jstork_custom/functions.php on line 62
姿勢制御は効率の良い運動、パフォーマンスを発揮する上でとても重要になります。
先にバランスが崩れることを予測して姿勢を安定させることで崩れないで動作できるからです。
崩れてから姿勢を治すでは効率が悪いのです。
脳卒中リハビリで必要な先行随伴性姿勢調整機能というシステム
わたしたちは運動を行う際に、効率よく遂行するために無意識的に姿勢の制御がなされています。
運動をする前に「この運動では重心があっちに移動するから先に反対側にちょっと重心をかけておこう」
運動中であれば「運動したら重心が変化したから、もう少しこっちに重心を移そう」といったようにです。
これを「先行随伴性姿勢調節」といいます。
よく教科書に載っている姿勢制御の例としては
上肢挙上時に三角筋の収縮の直前に体幹筋の収縮が確認されるというのが載っていると思います。
運動に伴う重心変化・身体動揺を先に予測し、身体動揺を最小限に抑えれるように、
運動中は前庭系や固有感覚からの情報をもとに身体動揺を抑えれるように筋活動を起こします。
姿勢制御の考えを実際に応用した症例の記事はこちら
準備的と随伴的の2種類の姿勢調節

出典https://onlineprerehabilitations.wordpress.com/
APAには、pAPAとaAPAの2つの構成要素からなります。
準備的先行性姿勢調節(pAPA)
これはpAPA(preparatory anticipatory postural adjustments)と呼ばれ、
運動に先立ち姿勢や重心の調整を行う機能です。運動開始の0.01秒前に姿勢調整のために体幹部の収縮を起こします。
フィードフォワード的に姿勢調整する機能といえるでしょう。
運動を行う際には
まず運動前野や補足運動野で
- 目的とする動作のプログラミング
- 目的の動作に先行する姿勢制御のプログラミング
という2つのプログラムが生成されます。
この2つのプログラムの経路は
目的とする動作は
・補足運動野や運動前野→一次運動野(4野)→皮質脊髄路→巧緻運動
姿勢制御では、
・補足運動野や運動前野→皮質網様体路→網様体脊髄路→姿勢制御
という経路で指令を伝達します。
姿勢制御は4野を介さないため少し早く網様体脊髄路を通って体幹部の抗重力筋を働かせます。
関連記事はこちら抗重力姿勢をとると覚醒がよくなるメカニズムは?
随伴的先行性姿勢調節(aAPA)
これはaAPA(accompanying anticipatory postural adjustments)と呼ばれ、運動が開始されると、
その運動の状況に随伴して姿勢調整を誘導します。フィードバック的に身体を安定させているといえるでしょう。
運動が開始されると、身体が少し動揺し重心が変化するわけなので、視覚や前庭、体性感覚情報に変化が起こります。
視覚からの情報は、
中脳の上丘に入力されて視蓋脊髄路を興奮させて眼球と頭頸部の協調運動をコントロールします。
視蓋脊髄路の記事はこちら『脳卒中リハビリと姿勢制御④~視蓋脊髄路と間質核脊髄路~』
前庭は
頭頸部の傾きや重心変化の情報を前庭神経核に入力し、頭頸部の平衡を保ったり、下肢伸筋を賦活します。
前庭脊髄路の記事はこちら『脳卒中リハビリと姿勢制御➂~前庭脊髄路~』
体性感覚情報は、
無意識的な深部感覚情報は小脳に入力され、小脳は網様体に投射しているため網様体脊髄路での姿勢調整に関与します。
網様体脊髄路の記事はこちら『脳卒中リハビリと姿勢制御➁~網様体脊髄路~』
"先行随伴性姿勢調節機能を抑制してしまう要素
①手すりやベッド柵、アームレストなどの支持物を強く上肢で支持している姿勢
②バランスクッションの上に立ったり、細い棒を渡るなど、極めて不安定な状態での運動
③椅子などの背もたれに寄りかかり、体幹の筋活動が少ない姿勢
④努力的で過剰に筋を発揮させている姿勢
参考図書・教科書